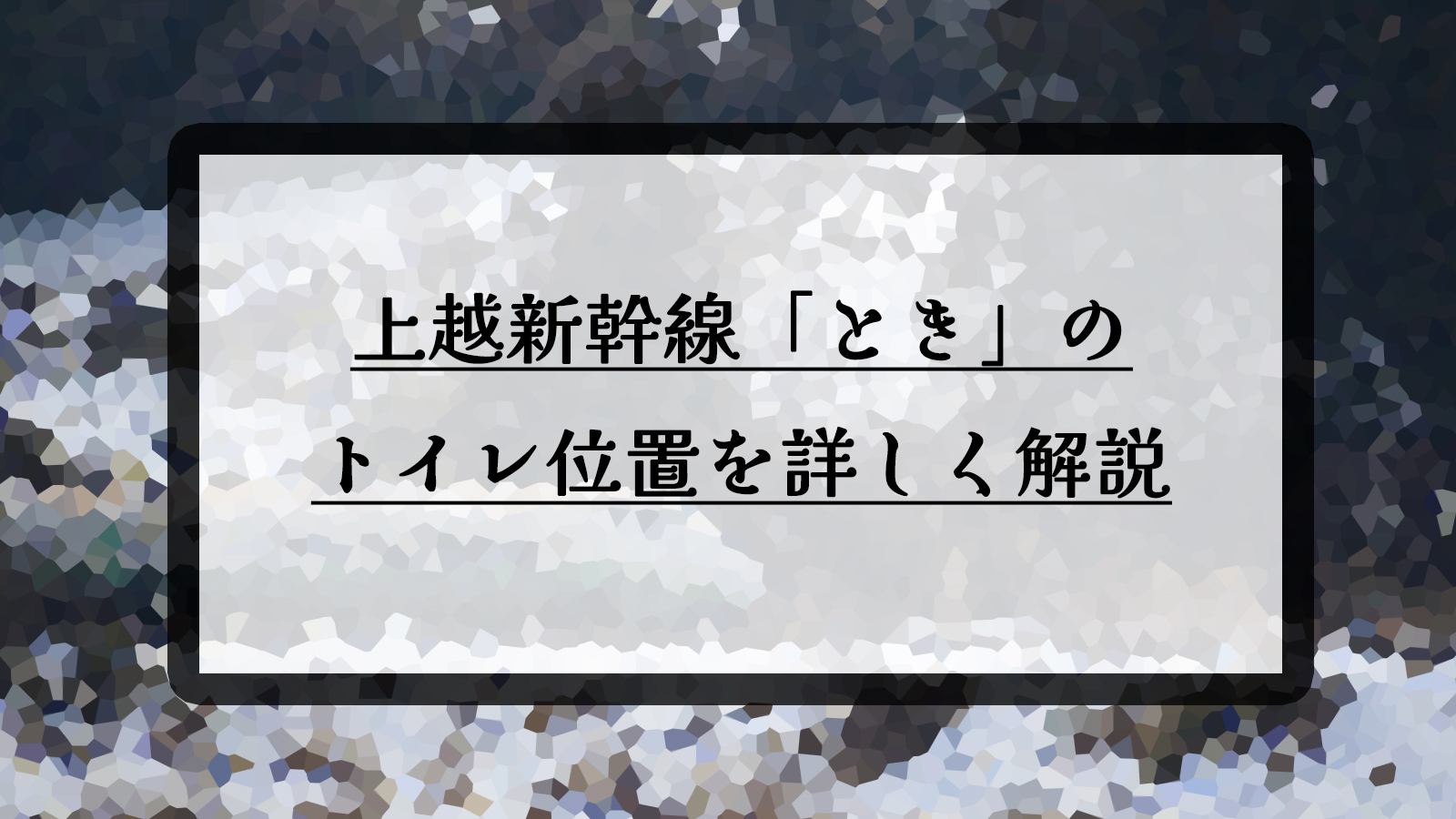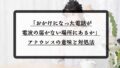上越新幹線「とき」は東京と新潟を結ぶ重要な鉄道ルートであり、観光客やビジネス利用者を含め、多くの乗客が日々利用しています。特に長距離移動となるため、車内の快適性は重要なポイントとなります。その中でも、トイレの位置や設備を事前に知っておくことは、快適な旅を過ごすための大切な要素です。
本記事では、上越新幹線「とき」における各車両のトイレ配置や設備の詳細について解説するとともに、混雑を避けるための方法や、スムーズに利用するためのヒントをご紹介します。また、トイレに関する便利な設備や他の新幹線との違いについても触れ、より快適な移動をサポートする情報をお届けします。事前に情報を把握しておくことで、移動中のストレスを減らし、快適な車内環境を維持することが可能です。
上越新幹線ときのトイレ位置の総合ガイド

上越新幹線ときのトイレの位置とは?
上越新幹線「とき」のトイレは特定の号車に設置され、車両の中央や端に配置されています。乗客が移動しやすいように計算された配置となっており、長距離移動の際にも便利に利用できます。
各車両のトイレ配置は、利用者の利便性を考慮して設計されており、特に多くの人が乗車する普通車には一定間隔で配置されています。一方、グリーン車やグランクラスでは乗客数が限られているため、トイレの配置も異なります。
さらに、車両の設計によってはトイレが中央にあるものや端にあるものがあり、利用しやすさが変わる場合があります。座席を選ぶ際には、トイレの位置を考慮すると、移動の手間を省くことができ、快適な旅を楽しめます。
トイレが設置されている車両と号車
すべての車両にトイレがあるわけではなく、特定の号車に設置されています。特に普通車・グリーン車・グランクラスでは設置位置が異なり、それぞれの車両の利用者に配慮した設計がされています。
普通車では、乗客が多いため、トイレの利用頻度が高くなります。そのため、複数の号車にトイレが設置されており、一定の間隔で配置されています。一方、グリーン車やグランクラスでは、乗客数が比較的少なく、トイレの混雑が少ないことが特徴です。また、グランクラスでは、特に清潔さや設備の充実度に重点が置かれており、より快適に利用できる環境が整っています。
また、車両ごとのトイレの配置には一定のルールがあり、先頭車両や最後尾車両には設置されていない場合があるため、乗車前にトイレの位置を確認しておくと、移動の負担を減らすことができます。
トイレの基本設備と種類
上越新幹線「とき」のトイレには、快適で清潔な環境が整えられています。基本的に洋式トイレが設置されており、温水洗浄便座が完備されているため、衛生的かつ快適に利用できます。
また、多目的トイレもあり、車いす利用者や高齢者、小さなお子様を連れた方にも配慮された設計になっています。多目的トイレには、広いスペースが確保されており、オストメイト対応の設備や手すりも完備されています。
さらに、おむつ交換台が設置されているため、赤ちゃんを連れた方でも安心して利用できます。授乳が必要な場合には、多目的トイレを利用することも可能です。一部のトイレには消臭機能や自動洗浄機能が搭載されており、より快適な空間が提供されています。
加えて、清掃が頻繁に行われており、常に清潔な状態が維持されるよう工夫されています。混雑時の対応策として、トイレ内には利用者のマナーを促す掲示があり、快適な利用環境を保つための工夫が施されています。
上越新幹線の号車別トイレ位置

1階のトイレ位置と特徴
1階には広めのトイレが設置されており、多目的トイレも完備されています。多目的トイレは車いす利用者や赤ちゃん連れの方、高齢者など、多様なニーズに対応できる設計になっています。十分なスペースが確保されており、オストメイト対応の設備や手すりも備えられています。
さらに、1階のトイレは通常の洋式トイレと比較して広めに作られており、混雑時でも利用しやすい設計です。また、一部の車両ではトイレ内に自動洗浄機能が搭載されており、衛生面の向上が図られています。頻繁に清掃が行われ、常に清潔に保たれているため、快適に使用することができます。
トイレの周辺には手洗い場やミラーが設置されており、手を洗ったり身だしなみを整えたりするのにも便利です。さらに、1階のトイレの近くには荷物置きスペースが設けられている場合があり、大きな荷物を持っている乗客も安心して利用できます。
1階のトイレは比較的アクセスがしやすく、多くの乗客に利用されるため、混雑する時間帯には少し余裕をもって利用するのがおすすめです。
2階のトイレ位置と比較
2階にはトイレが設置されていない車両が多いため、利用する際は1階へ移動する必要があります。これは2階建て車両の設計上の特徴であり、スペースの制約や座席数の確保を優先した結果です。特に混雑時には1階への移動が不便になるため、事前にトイレの位置を把握しておくことが重要です。
1階のトイレと比べて、2階にいる乗客は階段を利用して移動しなければならないため、身体に負担がかかることもあります。特に高齢者や荷物を持っている方は、座席選びの際にトイレの近くの1階席を選ぶことで、移動の手間を減らすことができます。
また、2階の座席からトイレまでの移動には時間がかかるため、乗車前や停車駅でのトイレ利用を考慮するのも一つの対策です。車内の混雑状況によっては、トイレ待ちが発生することもあるため、余裕をもって行動することが快適な旅につながります。
号車ごとのトイレの数と配置
トイレの数や配置は号車ごとに異なります。一般的に、普通車には一定間隔で設置されており、各号車の端または中央に配置されることが多いです。一方で、グリーン車やグランクラスは乗客の利用率が異なるため、トイレの数が限られている場合があります。
また、多目的トイレが設置されている号車もあり、車いす利用者や赤ちゃん連れの方に配慮された設備が整っています。多目的トイレは通常、車両の端に設置されることが多く、利用しやすい設計になっています。
トイレの配置を事前に確認することで、移動をスムーズにし、混雑を避けることができます。特に、長時間の移動を予定している場合は、座席の選択時にトイレの位置を考慮することで、より快適な旅を楽しむことが可能です。
「とき」号の各車両のトイレ事情

普通車のトイレと座席の配置
普通車では、多くの乗客が利用するため、トイレの位置を考慮した座席選びが快適な旅の鍵となります。トイレの近くに座席を取ることで、移動の負担を軽減できるだけでなく、急なトイレの利用にも対応しやすくなります。
また、普通車のトイレは車両ごとに一定の間隔で設置されており、端の車両ではなく、中間の車両にある場合が多いです。混雑時にはトイレ待ちが発生することもあるため、ピーク時を避けた利用計画を立てることが望ましいです。
さらに、普通車のトイレは頻繁に清掃が行われており、清潔な状態が保たれています。座席選びの際には、通路側を選ぶことで、トイレへのアクセスをよりスムーズにすることができます。また、長時間の乗車時には、トイレの近くの座席を予約しておくことで、移動のストレスを減らし、快適な旅を楽しむことができるでしょう。
グリーン車とグランクラスのトイレ
グリーン車やグランクラスでは、より快適で清潔なトイレが設置されています。これらの車両では、通常の普通車よりも高級感のある内装が施され、トイレの設備も充実しています。
グリーン車のトイレは広めに設計されており、落ち着いた雰囲気の中で利用できます。また、トイレ内の清掃頻度も高く、常に清潔な状態が保たれています。さらに、温水洗浄機能付きの便座が標準装備されており、快適な利用が可能です。
グランクラスのトイレはさらに上質な設備が備わっており、内装も高級感のあるデザインが採用されています。利用者の数が限られているため、混雑することがほとんどなく、落ち着いて利用できます。また、専用の洗面スペースが設置されている車両もあり、より快適な環境が提供されています。
グリーン車やグランクラスのトイレは、通常の車両よりも快適さを追求した作りになっており、長時間の移動でもリラックスして利用できるようになっています。
E7系とW7系の違いとトイレ位置
E7系とW7系ではトイレの配置が若干異なるため、乗車前に確認すると安心です。E7系ではトイレが車両の中央部に配置されることが多く、多目的トイレの設置も考慮されています。一方、W7系ではトイレの位置が車両の端に寄っている場合があり、移動のしやすさに違いが出ることがあります。
また、E7系はバリアフリー設計が強化されており、多目的トイレの広さや手すりの配置に工夫が施されています。これにより、車いす利用者や体の不自由な方でもスムーズに利用できるようになっています。W7系も基本的な設計は似ていますが、微細な違いがあるため、事前に配置を確認することが快適な移動につながります。
さらに、E7系とW7系ではトイレの清掃頻度や設備の仕様が異なる場合があり、グランクラスのトイレは特に上質な仕様になっています。どちらの車両を利用する場合でも、快適な移動をサポートするためにトイレの位置や設備の詳細を確認しておくことをおすすめします。
上越新幹線ときで驚いたは女性専用トイレがあったこと!ふたが自動で上がらなくて少し待ってしまったw pic.twitter.com/e8BeDbHngw
— よしみん (@jollypamyupamyu) October 5, 2024
トイレ利用時の混雑状況

ピーク時の混雑を避ける方法
発車直後や到着前は混雑するため、それ以外の時間帯を狙うとスムーズです。特に、駅を出発してから10~20分ほど経過すると、トイレの利用者が落ち着く傾向があります。また、昼間の時間帯や乗客の少ない曜日・時間帯を狙うことで、さらに快適に利用できるでしょう。
加えて、停車駅の多い列車では、短時間で混雑が解消されることが多いため、途中駅での乗降時間を利用してトイレに行くのも一つの方法です。逆に、長距離を走る列車ではトイレの利用が増えるため、食事前後や到着間際は混雑しやすくなります。
また、自由席の車両は乗客の回転が早く、トイレの混雑も一定のサイクルで変動するため、混雑しやすい時間を避けて利用するとスムーズに使えます。特に、車内の状況を見ながら適切なタイミングでトイレに行くことで、混雑によるストレスを減らせるでしょう。
リアルタイムの混雑情報取得
車内の電光掲示板やアプリでトイレの混雑状況を確認できます。最新の技術を活用した情報提供が進んでおり、新幹線内のデジタル表示パネルには、現在のトイレ利用状況がリアルタイムで表示されることがあります。これにより、利用者は混雑を避けてスムーズにトイレを使用することが可能です。
また、スマートフォンアプリを活用することで、乗車中のトイレの使用状況を確認することもできます。特に、座席から離れる前に混雑状況を把握することで、長時間待つことなくスムーズに利用できる利点があります。これらの情報を事前にチェックすることで、快適な旅をより一層楽しむことができます。
快適なトイレ利用のためのヒント
トイレを快適に利用するためには、事前に混雑状況を確認し、余裕を持って行動することが重要です。特に長距離移動では、駅での停車時間を活用して事前に済ませておくと、混雑時のストレスを減らすことができます。
また、トイレのマナーを守ることも大切です。使用後はしっかりと水を流し、次の利用者が気持ちよく使えるように心がけましょう。特に、多目的トイレを使用する際は、必要な方が優先的に利用できるように配慮することが求められます。
さらに、清潔な環境を維持するために、トイレットペーパーの使用量を適切にし、ごみは指定の場所に捨てるようにしましょう。手洗い後は、備え付けのハンドドライヤーを使用するか、持参したハンカチで手を拭くことで、衛生的な利用が可能になります。
これらのポイントを意識することで、トイレの混雑を減らし、全ての乗客が快適に利用できる環境を作ることができます。
上越新幹線マックスときのフラットシートに初めてのった。快適。12席しかなきので結構ゆったり。普通の1階席と同じ高さだし。トイレも近い。一番後ろなので思いきり倒せる。ただ、トイレ客が多く通過するのが難かなw
— 元トーシロ業界紙記者🌗非年金生活者(年金支給年齢前) (@tantantanuki) October 28, 2016
トイレに関する便利な設備

車内のコンセントとその利用
一部の車両にはトイレ近くにコンセントが設置されています。これにより、スマートフォンやタブレット、ノートパソコンなどの電子機器を充電しながら移動することが可能です。特に長時間の移動時には、バッテリー切れを防ぐために便利な設備となっています。
トイレ付近のコンセントは、主に通路側や手洗い場の近くに設置されていることが多く、誰でも手軽に利用できるようになっています。座席のコンセントを使えない状況でも、ここで充電ができるため、特に自由席を利用する際には役立つポイントです。
また、これらのコンセントは比較的利用者が少ないため、混雑時でも使用できる可能性が高いです。ただし、電源を長時間独占しないようにし、他の利用者にも配慮することが求められます。
新幹線のコンセントは電圧が安定しているため、多くの電子機器を安全に使用できますが、使用する機器によっては変換プラグが必要な場合もあります。快適な移動をサポートするために、充電ケーブルを事前に準備し、移動中でも電池切れの心配をせずに快適な旅を楽しめるようにしましょう。
授乳室や多目的トイレの利用方法
授乳室や多目的トイレを利用する際は、設置車両を事前に確認すると便利です。多目的トイレは車いす利用者やオストメイト対応設備が必要な方、小さな子どもを連れた方など、さまざまなニーズに対応するために設計されています。十分なスペースが確保されており、手すりや緊急ボタンが設置されているため、安心して利用できます。
また、授乳室については、特定の車両に設置されていることが多く、利用を希望する場合は事前にどの号車にあるのかを確認しておくとスムーズです。授乳室内にはカーテンや仕切りが用意されており、プライバシーを確保しながら安心して授乳できる環境が整っています。
さらに、多目的トイレの利用時には、必要に応じて車掌に声をかけることで、サポートを受けることも可能です。設備の詳細や利用方法を事前に把握しておくことで、より快適な移動ができるでしょう。
おむつ替えスペースについて
おむつ替え台が設置されている車両があり、小さな子ども連れでも安心です。これらの設備は主に多目的トイレ内に設置されており、広いスペースが確保されているため、ゆとりを持っておむつ替えができます。車両によっては専用のベビーベッド付きのスペースが用意されていることもあり、赤ちゃん連れの旅行者にとって利便性が向上しています。
さらに、おむつ替え台は折りたたみ式になっているため、使用しない時にはコンパクトに収納され、清潔な状態が保たれています。また、一部の車両では、おむつを捨てる専用のごみ箱が設置されており、衛生面にも配慮されています。
利用する際は、他の乗客の迷惑にならないように気を配り、長時間占有しないことがマナーとされています。長距離移動の際は、混雑を避けて早めに利用することで、より快適におむつ替えができるでしょう。
トイレの行き方と乗車時の注意点

座席からの移動のしやすさ
トイレに近い座席を選ぶと、移動の手間を減らせます。特に長距離移動の際には、トイレの近くの席を選ぶことで、混雑時や揺れのある車内でもスムーズに移動することができます。座席位置を事前に確認し、移動の負担を減らすことが快適な旅のポイントです。
また、通路側の座席を選ぶことで、他の乗客に迷惑をかけずにスムーズに移動できるため、頻繁にトイレを利用する可能性がある場合にはおすすめです。グリーン車やグランクラスでは、座席スペースが広めに設計されているため、より快適な移動が可能になります。
さらに、混雑しやすい時間帯や車両の構造を考慮し、トイレの利用が集中しそうな場所を避けた座席選びをするのも有効です。移動の負担を最小限に抑えつつ、快適な環境を確保するためには、トイレの位置だけでなく、通路の幅や荷物置きスペースの有無も事前に確認しておくとよいでしょう。
通路の幅と移動可能性
通路は十分な広さが確保されていますが、混雑時は注意が必要です。特に、乗降の多い駅では通路を通る人が増え、スムーズな移動が難しくなる場合があります。そのため、トイレへ行く際は混雑のピークを避けるのが理想的です。
また、上越新幹線の車両は一般的に通路が広めに設計されていますが、大きな荷物を持った乗客が多い場合、移動しにくくなることがあります。そのため、キャリーケースやバックパックを持っている場合は、できるだけ座席の下や荷物棚に収納するようにしましょう。
さらに、グリーン車やグランクラスでは通路が比較的広く、通常の普通車に比べて移動しやすい設計になっています。車いす利用者向けのスペースも確保されており、バリアフリー設計が施されているため、すべての乗客が快適に移動できる環境が整っています。
混雑時の通路移動をスムーズにするためには、周囲の乗客と譲り合いの精神を持ち、トイレを利用する際もできるだけ他の人の邪魔にならないように配慮することが大切です。
車いす利用者向けのトイレアクセス
車いす対応の多目的トイレが設置されており、快適に利用できます。これらのトイレは通常のトイレよりも広いスペースが確保されており、車いすでのアクセスが容易にできるよう設計されています。扉はスライド式になっていることが多く、力を入れずに開閉が可能です。
また、内部には手すりが設置されており、座った状態からの立ち上がりや移動をサポートします。さらに、オストメイト対応の設備が整っているため、ストーマ利用者の方も安心して利用できます。水洗機能や手洗いスペースも低めに設置されており、使いやすさが考慮されています。
多目的トイレの利用時には、優先順位を守り、必要とする方がスムーズに使用できるよう配慮することが求められます。混雑時は、事前にトイレの位置を確認し、利用のタイミングを調整するとより快適に過ごせるでしょう。
上越新幹線と他の新幹線との違い

北陸新幹線「はくたか」との比較
「はくたか」と比べると、トイレの設置位置や設備に若干の違いがあります。上越新幹線「とき」は、長距離移動を前提に設計されており、トイレの数が比較的多く配置されています。一方、「はくたか」は短距離区間の利用者が多いため、トイレの設置数がやや少なく、車両ごとの配置も異なります。
また、「はくたか」の一部車両では、トイレが車両の中央付近に設置されている場合があり、移動の利便性が考慮されています。上越新幹線「とき」の場合は、長時間乗車を快適にするために、多目的トイレや広めのトイレが完備されている点が特徴です。
さらに、清掃頻度や設備の仕様にも違いが見られます。「はくたか」のトイレは比較的コンパクトな設計が多い一方、「とき」は広めのトイレを採用し、混雑時の対応がしやすいようになっています。どちらの新幹線も清潔さには十分配慮されており、快適に利用できる環境が整っていますが、乗車する列車の特徴を理解しておくと、よりスムーズにトイレを利用できます。
「かがやき」との設備差
「かがやき」は停車駅が少なく、利用状況に違いがあります。そのため、長距離移動が主な利用目的となり、乗客の構成や車内の設備利用傾向が上越新幹線「とき」と異なります。
まず、停車駅が少ないことから、乗客の入れ替わりが少なく、一度乗車すると長時間同じ座席を利用することが一般的です。そのため、トイレの利用タイミングが比較的均等になりやすく、混雑が発生しにくい傾向にあります。しかし、食事時間帯や乗車前後のタイミングでは利用が集中することがあるため、計画的な利用が推奨されます。
また、「かがやき」はグリーン車やグランクラスの利用率が高い列車でもあるため、これらの車両に設置されているトイレは特に清潔に保たれています。トイレの設備も上質で、温水洗浄機能付き便座や自動消臭機能が備わっていることが多いです。一方で、普通車の乗客数が多い場合、車両後方のトイレが混雑しやすくなることもあるため、複数のトイレ位置を事前に確認しておくと安心です。
さらに、上越新幹線「とき」と比較すると、車両ごとのトイレ数が異なる場合もあるため、利用前に座席選びの際にトイレの配置を確認することが重要です。「かがやき」は長距離移動を快適に過ごすための設備が充実しており、トイレの清掃頻度も高いため、より快適に利用できる環境が整っています。
列車ごとの停車駅とトイレ利用の関係
停車駅の少ない列車では、事前にトイレを利用しておくと安心です。特に、長距離運行を行う列車では、次の停車駅までの間隔が長くなることがあり、タイミングを逃すとしばらく利用できない可能性があります。そのため、乗車前に駅のトイレを利用するのが推奨されます。
また、発車後すぐの時間帯や食事後の時間帯はトイレが混雑しやすく、待ち時間が発生することも考えられます。事前にトイレの位置を確認し、ピーク時間帯を避けることで、快適に利用することができます。さらに、車両ごとのトイレの配置を把握し、移動しやすい座席を選ぶことで、よりストレスなく過ごせるでしょう。
トイレに関するよくある質問

トイレはどのくらいの頻度である?
一定の間隔で設置されており、どの車両でもスムーズに利用できます。上越新幹線では、特に長距離移動の利便性を考慮し、車両ごとに均等な配置がなされています。そのため、乗車する車両にかかわらず、移動距離を最小限に抑えながらトイレを利用することができます。
さらに、普通車、グリーン車、グランクラスといった異なる車両ごとに利用者の数に応じてトイレの設置数が調整されており、混雑が発生しにくい工夫がなされています。トイレの清掃も定期的に行われており、常に清潔な環境が保たれているため、安心して利用できます。
また、上越新幹線のトイレはすべて洋式で、快適な温水洗浄便座が標準装備されています。これにより、長時間の移動でも衛生的かつ快適に過ごせるよう配慮されています。多目的トイレも設置されているため、車いす利用者や小さな子どもを連れた方でも安心して利用できる環境が整っています。
トイレの清掃状況は?
定期的な清掃が行われ、清潔に保たれています。上越新幹線では、快適な利用環境を維持するために、専門の清掃スタッフが定期的に巡回し、トイレの衛生状態をチェックしています。特に長距離運行の列車では、乗客の利用頻度が高いため、清掃の頻度も多く、常に清潔な状態を維持するよう努められています。
また、トイレットペーパーやハンドソープなどの備品も定期的に補充されており、不足することがないよう管理されています。さらに、最新の車両では自動洗浄機能が備わっているトイレもあり、使用後に自動的に洗浄・除菌が行われるため、より衛生的な環境が整っています。
混雑時でも快適に利用できるように、利用者自身も清潔に使用し、次の方のために気持ちよく利用できるように心がけることが大切です。
トイレ利用時のマナーについて
トイレを利用する際は、譲り合いの精神を持ち、清潔に利用することが大切です。特に、混雑時には長時間の占有を避け、必要な方がスムーズに利用できるよう配慮しましょう。
また、使用後はしっかりと水を流し、洗面台周りの水滴を拭き取るなど、次の利用者が快適に使えるよう心がけることも重要です。多目的トイレを使用する際は、車いす利用者や介助が必要な方が優先的に利用できるよう意識することが求められます。
さらに、トイレットペーパーの適切な使用や、備え付けのハンドソープを過剰に使用しないなど、節度ある利用もマナーの一環です。快適な車内環境を維持するためにも、乗客一人ひとりが意識してマナーを守ることが大切です。
上越新幹線のとき301号を使えば、湯沢中里スノーリゾートに無理なく早朝到着できます‼️
越後湯沢駅での乗り替え時間が大変短くなっていますので、きっぷは最寄り駅の指定席券売機などで事前購入しましょう!
あと、トイレは済ませておくか、E129系のトイレを使いましょう! pic.twitter.com/0eUDOCXu5f
— ゆっきぃ (@yuse2man) March 1, 2022
上越新幹線ときの設備全般

座席表と各車両の特徴
車両ごとに異なる座席配置や設備を事前に確認することで、より快適な旅を楽しむことができます。例えば、グリーン車やグランクラスでは座席間隔が広く、リクライニング機能も充実しているため、ゆったりとした移動が可能です。一方、普通車では、指定席と自由席で座席の配置や快適性が異なり、乗車時間や混雑状況を考慮して選ぶことが重要です。
また、トイレやコンセントの位置、荷物置き場の有無など、設備の違いも事前にチェックしておくと、移動中のストレスを軽減できます。特に長距離移動の場合は、座席選びが快適な旅の大きなポイントとなるため、公式サイトや車内マップを活用しながら、自分に合った席を確保するとよいでしょう。
指定席と自由席の選び方
トイレの近くの席を希望する場合は、指定席を選ぶと安心です。指定席では、事前に座席の場所を選択できるため、トイレに近い位置を確保しやすく、長距離移動の際にも快適に過ごすことができます。
特に、長時間の移動では、通路側の指定席を選ぶことで、トイレへのアクセスがよりスムーズになります。座席の間隔も比較的ゆとりがあるため、移動の際に他の乗客に迷惑をかけにくいのも利点です。また、自由席では席が確保できない場合もあり、トイレの近くの席を選ぶことが難しくなるため、安心して利用したい場合は指定席をおすすめします。
さらに、グリーン車やグランクラスでは、乗客の数が限られているため、トイレの混雑も少なく、より快適に利用できる環境が整っています。座席選びの際は、公式サイトや座席表を活用し、自分の移動スタイルに合った席を確保するとよいでしょう。
快適な旅をサポートする設備
トイレのほかにも快適な移動をサポートする設備が整っています。例えば、座席にはコンセントが備え付けられているため、スマートフォンやノートパソコンなどの電子機器を充電しながら移動できます。また、一部の車両にはWi-Fi環境が整っており、インターネットを利用しながら快適に過ごすことができます。
さらに、大型の荷物を収納できるスペースも設置されており、特に長距離移動の際には便利です。グリーン車やグランクラスでは、座席が広めに設計されており、リクライニング機能も充実しているため、より快適に移動することが可能です。
また、車内販売サービスを利用すれば、軽食や飲み物を購入することができ、旅の楽しみがさらに広がります。こうした設備を活用することで、長距離移動でもストレスなく快適に過ごすことができます。
まとめ

上越新幹線「とき」のトイレは車両ごとに異なるため、事前に配置を確認するとスムーズに利用できます。特に長距離移動では、トイレの位置を把握しておくことで移動の負担を軽減し、快適な旅を楽しむことができます。
また、トイレの利用が集中する時間帯を避ける工夫をすることで、待ち時間を短縮できるでしょう。例えば、発車直後や到着前のタイミングは混雑しやすいため、食事の前後や停車時間を活用して余裕を持った利用を心がけることが大切です。
さらに、多目的トイレの利用が必要な場合は、どの車両に設置されているかを確認し、移動しやすい座席を選ぶことが重要です。公式サイトや車内マップを事前にチェックし、自分のニーズに合った車両を選ぶことで、より快適な旅を実現できるでしょう。