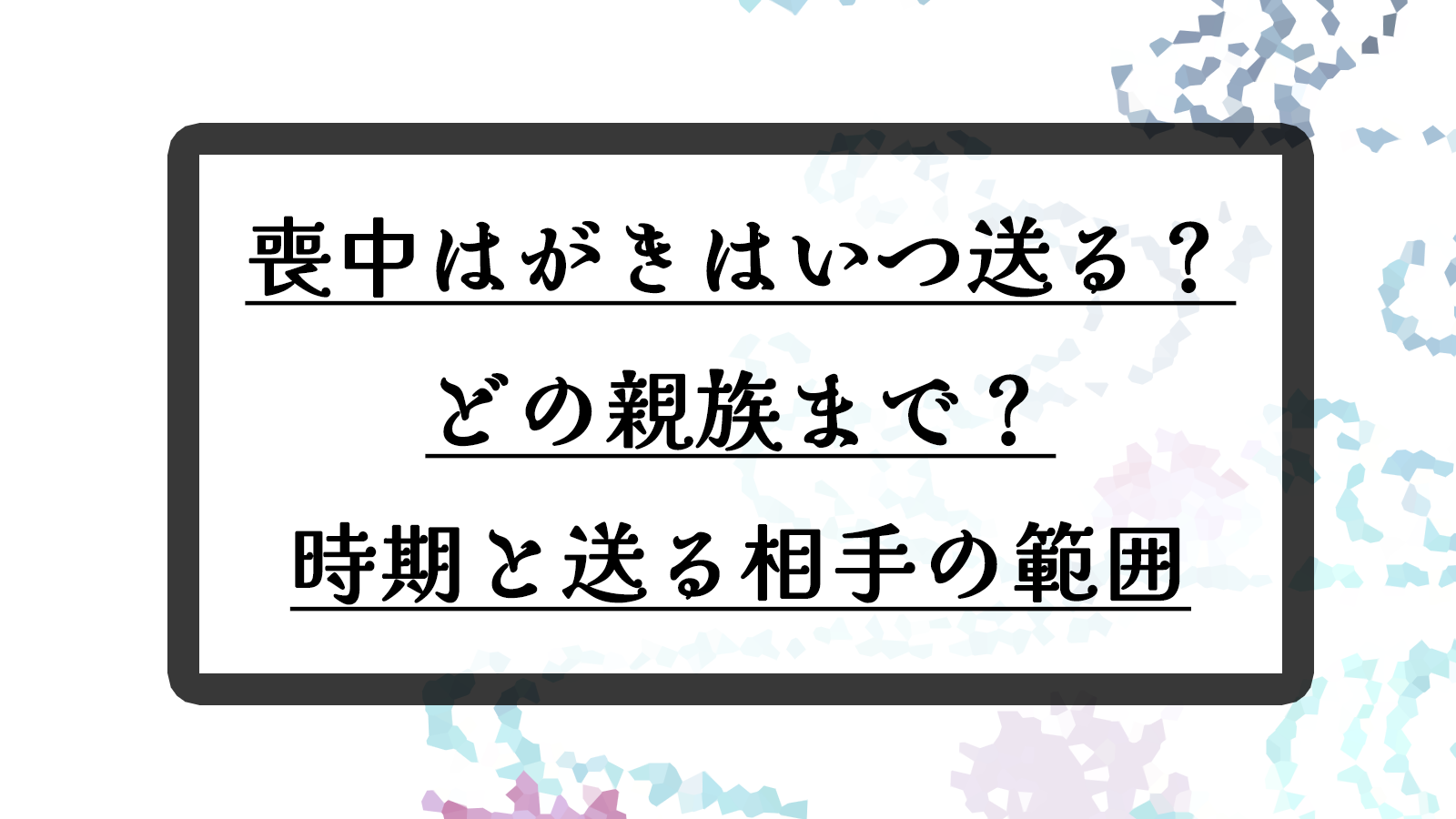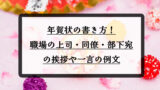近い親族に不幸があった際に必要となる喪中はがき。
今まで見たことのある方の方が多いと思います。
ですが、通年行われる行事ではないため、喪中はがきに関するマナーがわからないことも多いと思います。
喪中はがきはいつ送るべきなのでしょうか?
誰に送る必要があるのでしょうか?
親族にも送る必要があるのでしょうか?
これらの疑問に答えるための情報をまとめました。
喪中はがきを送るタイミング
まず、喪中はがきの重要性とその役割を理解することが大切です。
喪中はがきとは、具体的にはどのようなものなのか、詳しく解説します。
喪中はがきの定義
近親者が亡くなった直近の1年間に送る挨拶状です。
喪中期間中、新年の挨拶や年賀状の送付を控える意図を、年賀状を送りそうな相手にあらかじめ伝えるために使われます。
では、喪中はがきはいつ送るのが最適なのでしょうか?
相手が年賀状の準備をする前に通知するのが理想的です。
年賀状の販売と受付の開始時期
通常、年賀状は11月1日から販売開始されます。
このため、喪中はがきは11月初旬に届けるのが理想です。
郵便局は12月15日から年賀状の受付を開始します。
したがって、遅くとも12月中旬までに配送することが望ましいです。
これらの情報から考えると、相手が年賀状の準備を始める時期を見越して、11月初旬から12月中旬にかけて喪中はがきを送るのが適切です。
ただし、このルールはその年の11月までに家族に不幸があった場合に限ります。
12月に不幸があった場合の対処法
喪中はがきの準備が間に合わない場合、受け取った年賀状に対する返信として使うこともあります。
1月7日の松の内が過ぎた後に届くように、寒中見舞いとして送ると良いでしょう。
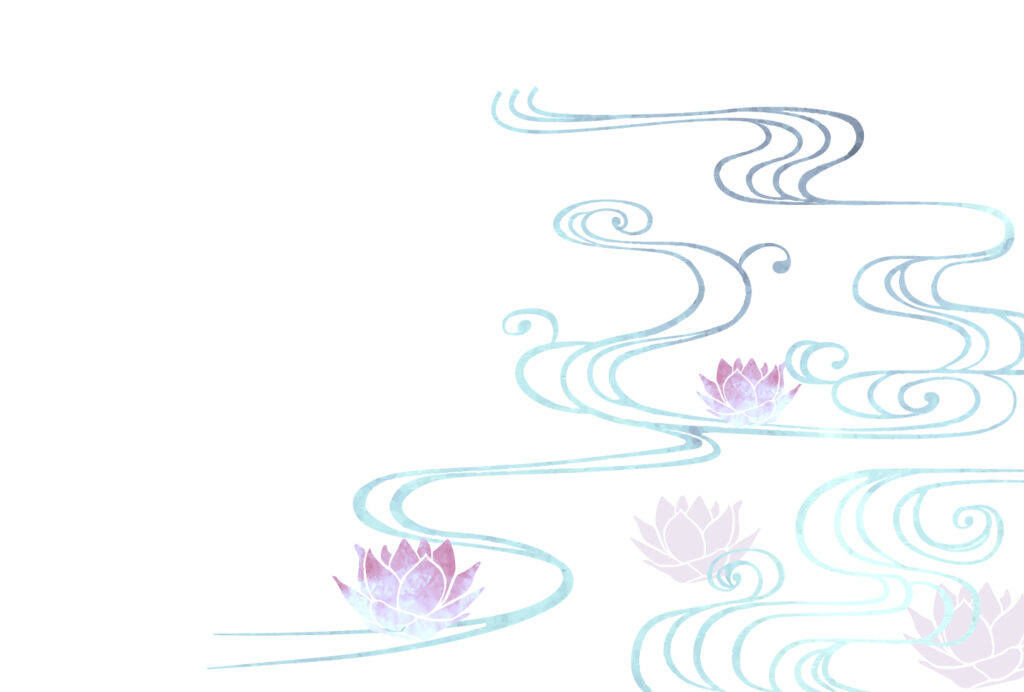
喪中はがきは誰に送る必要があるか?
喪中はがきを送る必要がある相手について考えてみましょう。
一般的に、以下のような人たちが喪中はがきの受取人となります。
- 定期的に年賀状を交換している人たち
- 普段から年賀状を送り合っている人たち
- その年に特にお世話になった人たち
- 故人と年賀状のやり取りをしていた人たち
- 故人の葬儀に参列した人たち
たとえば、普段から年賀状を交換している友人、職場の同僚、上司、先生、結婚の仲介者などがこれに当たります。
また、故人と年賀状を交換していた知り合いや友人も、喪中はがきを送るべき対象者となることがあります。
喪中はがきは親族に送る必要はある?
では、喪中はがきを親族にも送るべきなのでしょうか?
この点を理解するためには、喪中はがきの本当の意味を把握することが重要です。
×故人の訃報を知らせるため
×年賀状を送らないように依頼するため
これらは喪中はがきの本来の意味ではありません。
◎新年の挨拶や年賀状の送付を自粛する意志を伝えるための挨拶
喪中はがきは、喪に服している期間中、新年の挨拶や年賀状の送付を控える意思を示すものです。
つまり、年賀の欠礼を伝えるものと言えます。
この意味を考えれば、親族にも送ることが礼儀とされています。
ただし、親族間では既に状況が共有されていることも多く、喪中はがきを送ることがかえって失礼にあたる場合もあります。
このような場合は、喪中はがきの送付を省略することもありますが、省略することが不適切だと考える人もいるかもしれません。
このようなケースでは、地域や家庭によって対応が異なるため、問題が生じそうな場合は事前に電話で相談するなど、状況に応じた柔軟な対応が推奨されます。
喪中はがきを送るべき親戚がいる場合も
親族間で既に事情が共有されている場合、喪中はがきを省略することがあります。しかし、特定の状況では親戚へ送ることが適切です。
主に、まだ訃報を伝えていない親族がこれに当たります。
遠く離れた親戚や、普段あまり連絡を取り合っていない親族は、最近の家族の状況を把握していないことが多いため、喪中はがきを送ることを考慮することが望ましいです。
まとめ
この記事では、喪中はがきの送る時期、対象者、特に親族への対応について説明しました。
喪中はがきは、新年の挨拶を控える意思を伝える目的で用いられます。
このため、相手が年賀状を準備する前に喪中はがきを送るのが理想的です。
また、通常年賀状のやり取りをしている相手に対しても、喪中はがきを送ることが適切です。
親族に関しては、緊密な関係がない場合には、無理に心配する必要はありません。
何か疑問がある場合は、気軽に相談するなどの柔軟な対応が望ましいです。