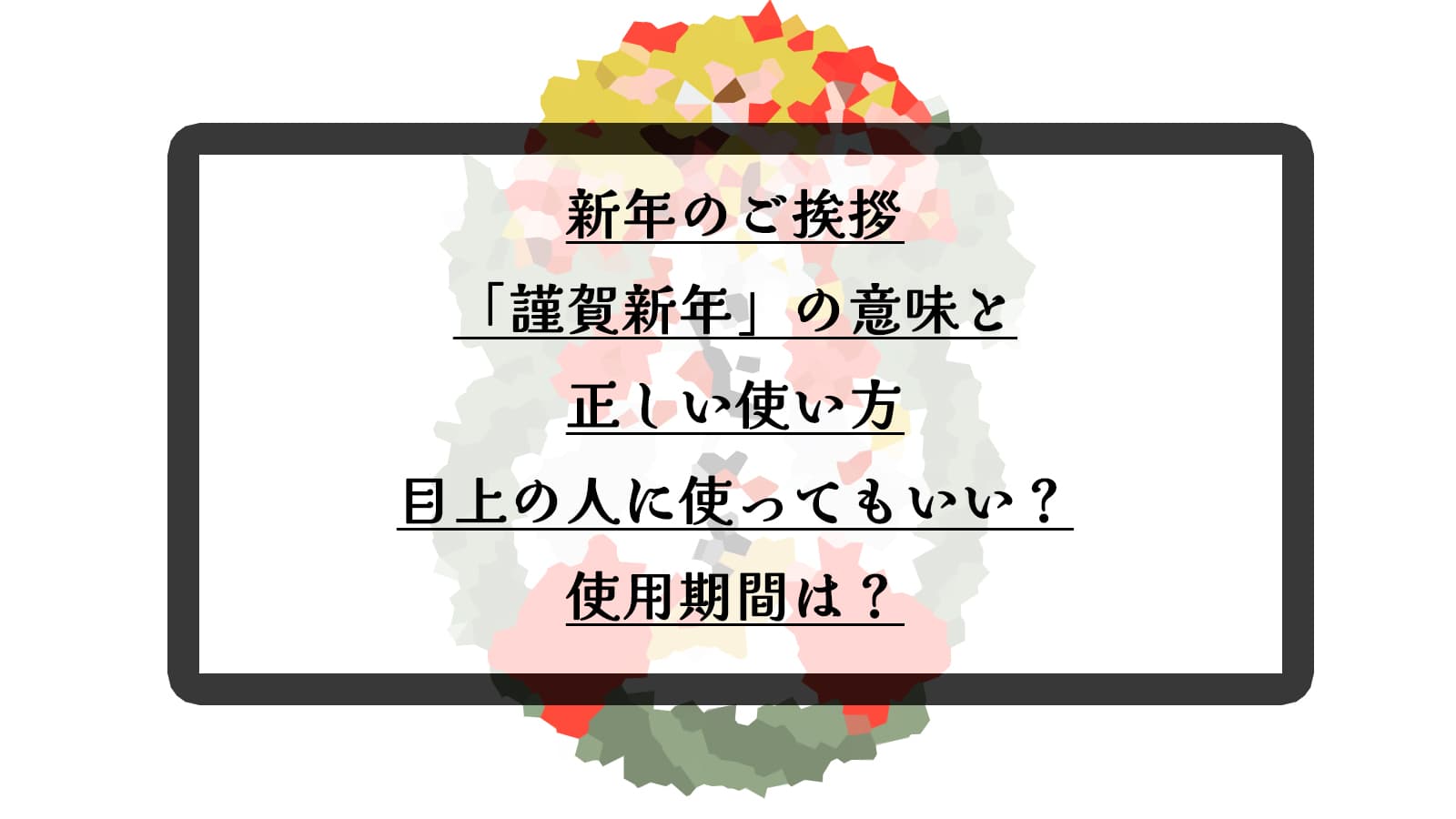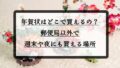年賀状でよく目にする「謹賀新年」という文字。
これが具体的にどんな意味を持つのか、ご存知ですか?
毎年使っていても、その詳細を知らないという方も少なくないでしょう。
特に、目上の方にこの言葉を使っても問題がないのか、気になるところですね。
また、「謹賀新年」はいつまでに使える言葉なのでしょうか?
これらの疑問を解消するため、謹賀新年の意味と使い方について調べてみました。
謹賀新年の意味とは?
「謹賀新年」とは、新しい年を迎えるにあたって、敬意を表して喜びを伝える言葉です。
「謹賀新年」は、「謹んで新年の喜びを申し述べる」という意味があります。
読み方は「きんがしんねん」で、主に年賀状の冒頭に使われることが多いですね。
こうした賀詞には様々な形がありますが、一文字や二文字、さらには四文字や文で表現されることも。
- 一文字の賀詞:寿、福、賀、春、禧
- 二文字の賀詞:賀正、賀春、迎春、頌春、慶春
- 四文字の賀詞:謹賀新年、謹賀新春、恭賀新年、恭賀新春
- 文の賀詞:明けましておめでとうございます、新年おめでとうございます、新春のお慶びを申し上げます、HAPPY NEW YEAR
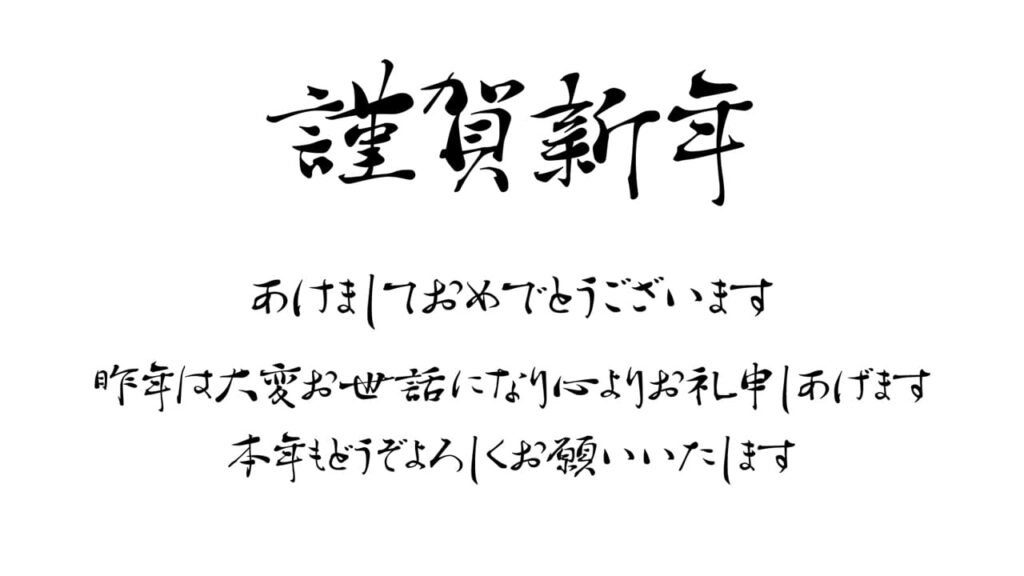
謹賀新年を目上の人に使うのは間違い?
目上の人に対して「謹賀新年」を使うことは間違いではありません。
「謹んで新年のお喜びを申し上げます」という敬意ある表現が含まれているからです。
したがって、目上の方にも適切です。
ただし、賀詞には使用する相手によって注意が必要なものもあります。
例えば、一文字や二文字の賀詞は、敬意を表す要素が省略されているため、目下の人や友人には適切でも、目上の人には不適切とされることがあります。
例としては以下のように省略されています。
- 寿:めでたい
- 福:幸せ
- 賀正:正月を喜びます
- 迎春:春を迎えます
これらの賀詞は簡潔に祝意を表しているため、目上の方には使用を控えるほうが無難です。
文の賀詞を使うのは目上の人に失礼?
文の形での賀詞は、相手を選ばずに使える表現です。
たとえば、「明けましておめでとうございます」や「新年おめでとうございます」は、どのような相手に対しても使うことができます。
「新春のお慶びを申し上げます」や「HAPPY NEW YEAR」も同様に、広範囲で使える表現です。
会社の上司や先輩など目上の人に対しては、「謹賀新年」や「新春のお慶びを申し上げます」などの敬意を含んだ賀詞が好まれます。

謹賀新年はいつまで使える?
「謹賀新年」という言葉を使える期間には一定の範囲があります。
これは主に「松の内」と呼ばれる期間に限られます。
松の内とは、新年を祝う期間のことで、お正月の飾り物(門松など)を飾っておく期間です。
一般的には1月7日までとされていますが、地域によっては1月15日までとする場合もあります。
また、年賀郵便の受付は毎年12月15日から翌年1月7日までとなっており、この期間に届けられる年賀状に「謹賀新年」と記されることが多いです。
そのため、謹賀新年を使う適切な期間としては、1月7日までが一般的と言えるでしょう。
あとがき
ここでお伝えした謹賀新年の意味や使い方について理解していただけたでしょうか。
目下の相手や友人への使用にはそれほど気を使わなくても大丈夫ですが、目上の方に対しては、最低限のマナーを守ることが大切です。
特に、シンプルな二文字の賀詞を使う場合は、相手に対して不適切な印象を与えないよう注意が必要です。
新年の挨拶は、相手を敬う心を形にしたものですので、適切な年賀状の準備を心がけましょう。