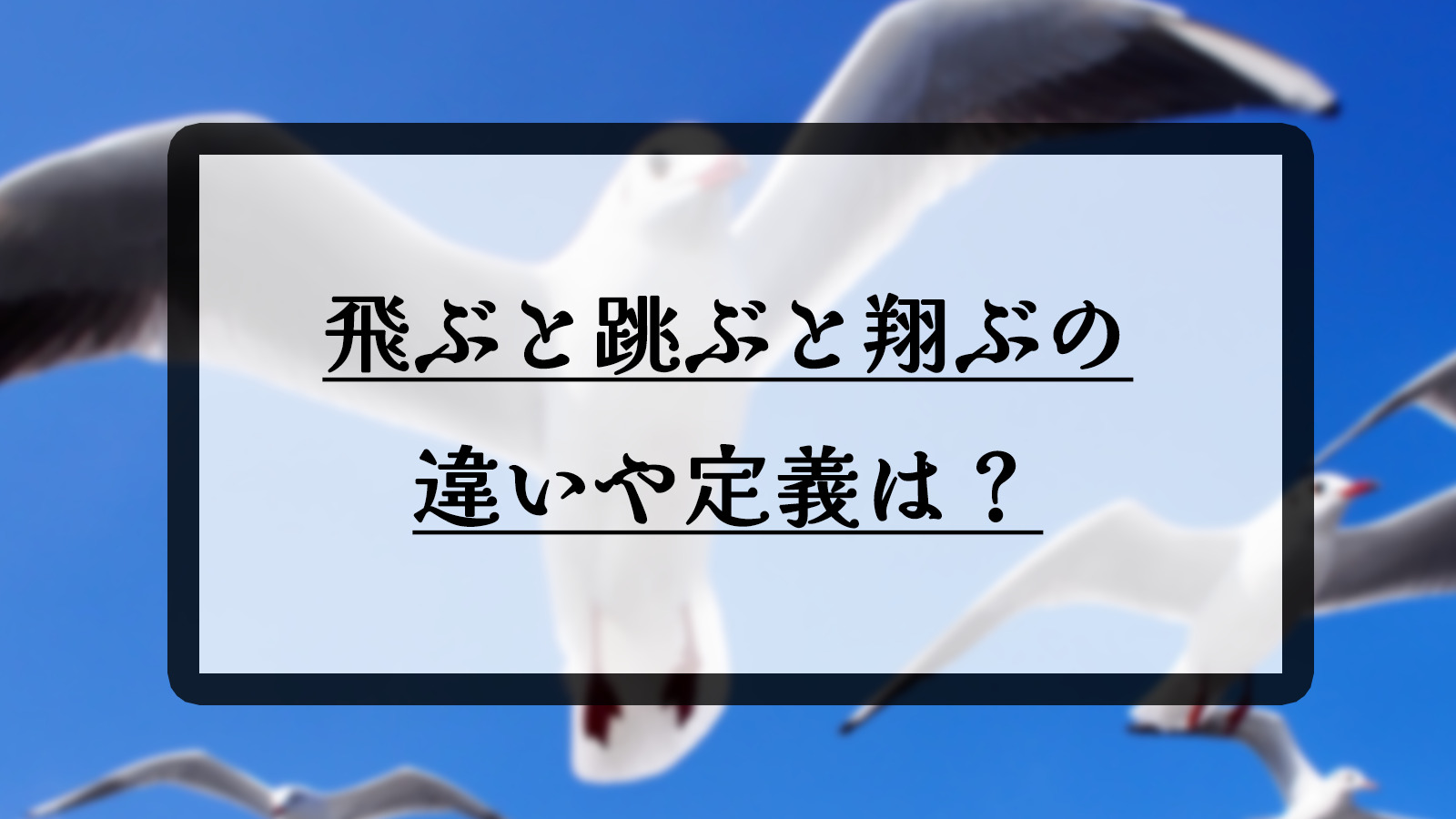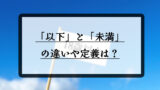飛ぶと跳ぶと翔ぶの違い
「飛ぶ」は空中での移動や飛行のイメージが強く、「fly」に近いニュアンスです。
「跳ぶ」は空中への一瞬の跳躍や「jump」のような動作です。
「翔ぶ」は非常に高い位置での飛行や、自由に空を飛ぶ比喩的な表現です。

飛ぶと跳ぶと翔ぶとは?
例えば、航空機や風に乗るような移動は「飛ぶ」、バスケットボール選手のような瞬時の跳躍は「跳ぶ」となる。
「とび上がる」の場合。
熱気球やグライダーのように高く舞い上がる動きならば「飛び上がる」と表現する。
逆に、サッカー選手がヘディングのために跳ねるような動作は「跳び上がる」となる。
魚が水から飛び出す場合
トビウオのように水面を滑るような動きであれば魚が「飛ぶ」。
水面から急にとび出てくる動きであれば魚が「跳ぶ」と記述する。
「飛びおりる」行為は、空中を通って地面に向かう動きを指し、「飛び降りる」と一般的には言います。
なお、「飛び下りる」と「飛び降りる」の表現は混用されることがありますが、通常は「飛び降りる」と記述されることが多いです。
また、「とび跳ねる」の場合。
車が水たまりを通った時に水が飛んでくるのは、水自体は動いていないので「飛び跳ねる」
犬がはしゃぐような動きならば「跳びはねる」となる。
その際、「はねる」は文字の組み合わせとして、見た目がよいひらがなで表記される。
「高とび」の場合。
スポーツの文脈では「棒高跳び」や「走り高跳び」として「跳ぶ」を使用。
その場から遠のく動きを示す際は「高飛び」として「飛ぶ」を選びます。
なお、「飛ぶ」は「ニュースが飛ぶ(迅速に拡散する)」「計画が飛ぶ(中止になる)」「現場に飛ぶ(急いで駆けつける)」など、様々な文脈で使われる。
「とぶ」の文字には「飛ぶ」や「跳ぶ」以外にも、「翔ぶ」という漢字が存在します。
この「翔ぶ」は、雲を自由に飛び回るドラゴンや幻想的な存在が用いるものとして、詩的な表現として使われることが多いです。
そして、辞書においては「翔」の訓読みとして「とぶ」が必ずしも採用されていないが、歴史的な文献には「とぶ」という読みが確認され、それが当て字という訳ではないことが示されている。