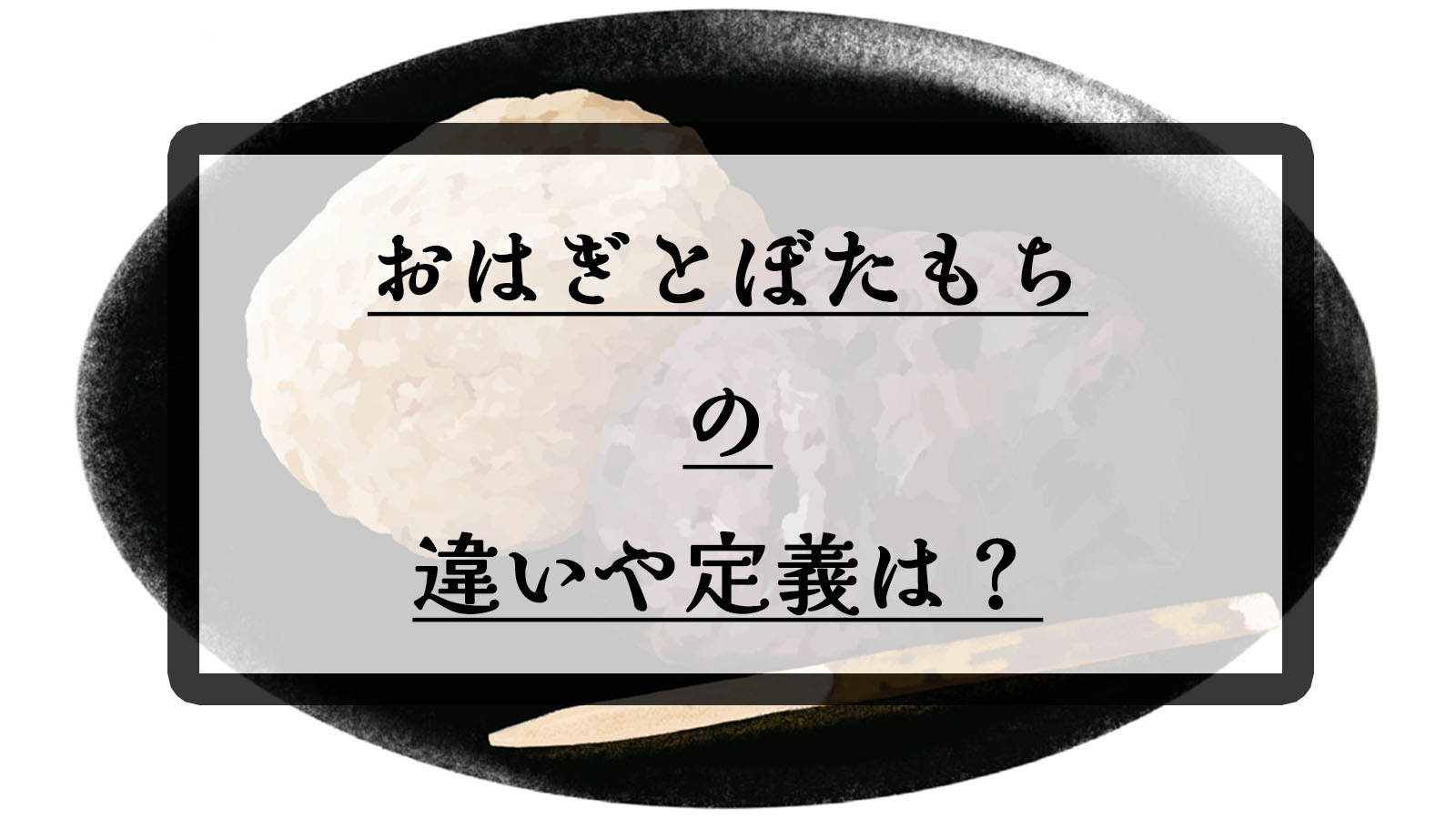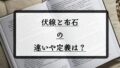おはぎとぼたもちの違い
ぼたもちは、春のお彼岸に合わせて多く食べられる和菓子。
おはぎは、秋の彼岸に合わせて多く食べられる和菓子。
大きさや材料に若干の差があります。

おはぎとぼたもちとは?
「おはぎ」と「ぼたもち」は似た外見や風味を持つ和菓子ですが、名前の由来、季節ごとの使い分け、大きさや使用する材料などに微妙な差異が存在します。
ぼたもちは、春の彼岸に合わせて食べられることが多く、「牡丹餅」と書かれ、華やかな牡丹の花から名付けられました。
対して、おはぎは秋の彼岸に多く作られ、「御萩」と書かれ、ふわりとした萩の花をイメージして名づけられています。
かつては、春にはぼたもち、秋にはおはぎと季節に応じた呼び名が使われましたが、現在ではこの区分はほとんど用いられません。
また、夏と冬に食べられるこれらの和菓子は、それぞれ「夜船」と「北窓」と呼ばれることもあります。
これは製法や食べられる時期に関する言葉遊びから来ています。
特に「おはぎ(ぼたもち)」は静かに作られることから、その名前がつけられました。
地域によっては、おはぎとぼたもちを大きさによって区別する習慣もあります。
通常、おはぎは小さく、ぼたもちは大きく作られ、これは各々が連想させる花の大きさに基づいています。
あんこの種類による呼び名の違いも見られます。
おはぎには粒感のある「つぶあん」を使用することが多く、ぼたもちには滑らかな「こしあん」が使われます。
これは、秋と春の小豆の特性に合わせた選択とされています。
さらに、「ぼたもち」はもち米を、「おはぎ」はうるち米を使用するなど、使われる米の種類やトッピング(あんこやきな粉)、餅の加工状態によって名前が変わることがありますが、これらの区分は地域や店舗によって異なり、一般的な規則としては確立されていません。
最後に、「おはぎ」「ぼたもち」は餡を纏った餅の一種で、「あんころもち」とも呼ばれますが、この中でも「あんころもち」は餅を完全につぶして作り、「おはぎ」「ぼたもち」は米粒を残す程度につきます。
このため、地域や人によって「全殺し」や「半殺し」といった呼び名で区別されることもあり、また「あんころもち」が大福のように餡を餅で包む形で呼ばれることもあります。
https://sakudori.com/chigai00020/